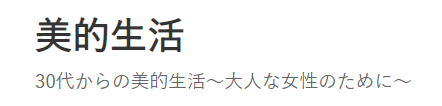あなたは「すあま」を食べたことがありますか?関東の人ならば「ああ、あの和菓子ね」と答えるでしょう。でも、「すあま」は関西ではほとんどど知られていません。
「すあま」とはどんなお菓子なのか、「すあま」とよく似ている「ういろう」や「すはま」との違いについてもお話します。
「すあま」とは

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 漢字表記 | 寿甘、素甘 |
| 地域 | 関東中心 |
| 他の名前 | つるのこ餅、鳥の子餅、しんこもち |
| 材料 | 上新粉、砂糖 |
| 製造過程 | 上新粉とお湯で練り、砂糖を加えて蒸し、形作り |
| 色 | 食紅でピンクにしたり、縁だけをピンクにしたり |
| 触感 | やわらかく、もちもち |
| 特徴 | 手や歯にくっつきやすい |
| 関西での誤解 | かまぼこと勘違いされることがある |
すあまとは漢字で「寿甘」または「素甘」と書く和菓子で、関東を中心に食べられています。「すあま」と呼ばれる以外に、「つるのこ餅」「鳥の子餅」「しんこもち」と呼ばれたりもします。
関東の人ならばみんなが小さいときから知っているお菓子ですが、関東以外の地域ではほとんど知られていません。見た目がかまぼこに似ているため、関西の人に見せるとかまぼこだと勘違いして、食べてびっくりということもあるようです。
すあまは素朴な甘い味で懐かしさを感じさせる餅菓子です。材料はお米から作る上新粉や砂糖、上新粉にお湯を加えて練り、砂糖を加えて蒸してから巻きすで巻いて形を整えて完成します。
色は食紅を加えて全体をピンクにしたり、色付けしたものを包んでかまぼこのように縁だけをピンク色にしたりします。触感はやわらかくてもちもちしていて、食べると手や歯にくっつきやすいです。
ういろう・すはまとの違い

「すあま」は見た目や名前が「ういろう」「すはま」に似ていますが、味や食感に違いがあります。
| 項目 | すあま | ういろう | すはま |
|---|---|---|---|
| 漢字表記 | 寿甘、素甘 | 外郎 | 州浜 |
| 主な地域 | 関東 | 名古屋、小田原、伊勢など | 京都 |
| 材料 | 上新粉、砂糖 | 米粉、砂糖、白玉粉 | 州浜粉(青豆や大豆)、砂糖、水飴 |
| 製造過程 | 蒸し、臼でつく | 蒸し | 練り |
| 食感 | もちもち | もちもち | しっかり |
| 色 | ピンクなど | 一般的に白 | 茶色、黒、緑、ピンクなど |
| 形状 | 羊羹、かまぼこ形 | 羊羹形 | お団子形(串に刺す場合もあり) |
| 特徴 | 手や歯にくっつきやすい | 中国起源、薬の口直しとして | 大豆の風味、家紋に由来 |
「ういろう」とは
「ういろう」とは漢字で「外郎」と書く和菓子です。1368年、中国が明王朝に変わったときに九州の博多に亡命してきた陳外郎(えんういろう)さんは、薬や医学の知識があったことからせきやたんに効果がある透頂香(とうちんこう)を売り出します。
透頂香は評判になったのですが、名前が難しいことから、外郎さんの薬ということで、彼の外郎という名前で人々に広められます。
そののち、薬の口直しとして中国から持ってきた餅菓子が、薬の外郎と似ていることから、そのお菓子も外郎と呼ばれるようになり、外郎(ういろう)が広まりました。
現在、「ういろう」は名古屋、小田原、伊勢、京都、神戸、山口、徳島、宮崎などで売られています。
ういろうは、米粉、砂糖、お湯を方に混ぜて蒸して作ります。
「すはま」とは
この投稿をInstagramで見る
スポンサーリンク
「すはま」とは漢字で「州浜」と書く和菓子です。州浜とは、河口にできる三角州などをもとにして作られた家紋をさします。
「すはま」の切り口はこの「州浜」の家紋によく似ていることから、このお菓子の名前は「すはま」となりました。すはまは鎌倉時代中期に京都で生まれ、現在も京都で売られています。
「すはま」は州浜粉を使って作ります。州浜粉は、青豆や大豆を炒って粉にしたものです。その州浜粉に砂糖と水飴を加えて練り上げると「すはま」はできあがります。
「すはま」は甘さの中に大豆の香ばしさが感じられるお菓子で、食感はしっかりしています。きなこの茶色、黒砂糖の黒、抹茶の緑、ピンクなどの色があり、三色団子のように串に刺した「すはま団子」も人気です。
すあま、ういろう、すはまの違い

すあまとういろうは見た目ももちもちした食感などがよく似ていますが、材料もよく似ていてどちらも上新粉と砂糖を使います。けれど、ういろうはさらに白玉粉を加えるところがすあまと違います。
すあまとういろうはどちらも蒸して作るのですが、すあまは蒸し上げてから臼でつくという工程が加わります。
ういろうは生地を練って蒸したらできあがりですが、すあまは蒸した後に臼でついて砂糖と塩を加えていき、もう一度蒸気にかけてから着色して形を整えます。
すはまは名前こそすあまによく似ていますが、見た目も風味もすあまとはまったく違います。
すはまの材料は大豆と青豆をひいたもの、それに砂糖と水飴を加えて練っているので、すはまは大豆の風味がよく出ています。
すあまやういろうは羊羹、またはかまぼこのような形で売られていますが、すはまは串に刺さってお団子の形で売られていることも多いです。
食べたことがない人もぜひご賞味を!
もちもちしていてやさしい甘さがあってはじめて食べてもなんだか懐かしさを感じさせてくれる「すあま」。
小さい頃は食べたなあという関東の人も、関東に来てはじめてすあまを見た、という関西の人も、「すあま」をご賞味ください。
もちもちした食感と甘さは、お茶受けのお菓子に合いますから、日本茶のお供にぜひどうぞ。