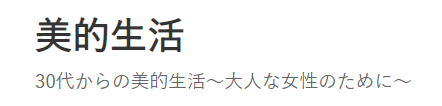どこの家の食卓にも置いてある調味料の一つといえば醤油ですよね。お刺身を食べるとき、煮物の味付けなど、和食を食べるときにはこれがないと困る、という醤油。醤油には濃口と淡口があります。
濃い色の濃口醤油に、色が薄くて味は薄口?に見える淡口醤油。スーパーなどに買いに行くとどちらの醤油も売られています。
どちらを選ぶかは好みによりますが、関西と関東ではこの醤油の選び方に違いがあります。関西では淡口醤油、関東では濃口醤油を選ぶ人が多いですが、それはどうしてなのでしょうか?
醤油の好みの違いの理由は?濃口醤油と淡口醤油、どうして好みが違うかについて考えました。
醤油の種類
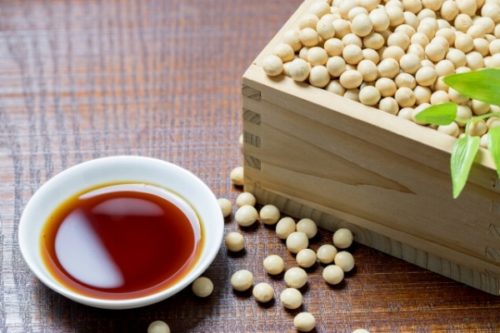
醤油はどれも大豆、小麦、麹、塩、そして水を使って作ります。しかし、原料の割合を変えたり熟成期間を買えることによって、味や香りに違いが出ます。味や香りの違いによって、醤油は次の5種類に分かれます。
| 醤油の種類 | 主な特徴 | 使用される地域 | 塩分量 | 適した料理 |
|---|---|---|---|---|
| 濃口醤油 | 色が濃く、香りが強い | 東日本、全国 | 標準 | 煮込み料理、炒め物 |
| 淡口醤油 | 色が薄く、香りが少ない | 関西 | 多い | 野菜の煮物、炊き込みご飯 |
| たまり醤油 | 大豆の旨味が強い | 中部地方 | 標準 | お刺身、寿司、タレ |
| 再仕込み醤油 | 色が濃く、味が濃厚 | 山陰地方、九州 | 標準 | 刺し身、寿司 |
| 白醤油 | 色が非常に薄い | 愛知県三河地域 | 不明 | 野菜、炊き込みご飯 |
濃口醤油
もっとも一般的なのが濃口醤油です。東日本でよく使われていますが、日本全国で見ても醤油の生産量のうち約8割がこの濃口醤油です。
濃口醤油は蒸した大豆と同じ量の炒って砕いた小麦で作った麹に食塩水を加えて熟成させ、できたもろみを撹拌させて熟成させて作ります。
濃口醤油は作る料理の種類を選ばずこれ一本ですべての料理をするという人も多く、しっかりと味をつけたい料理に適した醤油です。
煮込み料理を作ったり、炒め物にかけたり、食材にそのままかけるなど、いろいろな使い方をすることができる万能な醤油です。
淡口醤油
関西で作られたのがはじめだと言われている醤油です。特徴は色が薄いこと、そして香りが少なめなことです。
色が薄いことから味も薄めで塩分が少ないように見られがちですが、実際の淡口醤油の塩分量は濃口よりも多いです。
淡口醤油は色が薄いですから食材を引き立てることができ、料理は上品に仕上がります。
香りが薄いためにつけやかけるときにはあまり向いていませんが、食材を引き立てることができることから、野菜の煮物や炊き込みご飯を作るとき、またはうどんのつゆによく使われます。
たまり醤油
中部地方でよく作られているのがたまり醤油です。大豆を蒸して作った味噌玉に麹を受け付けて塩水に仕込み、1年間熟成させて作ります。
大豆と少量の小麦を使って作るため、大豆の旨味や香りが強く、とろみがあることが特徴です。
コクやテリが付きやすいことから、お刺身や寿司のつけ醤油として、またうなぎや焼鳥のタレにも使われます。
加熱すると美しい赤みが帯びることから、煎餅やあられのつけ焼きとしてもよく使われます。
再仕込み醤油
現在では全国的に作られていますが、山陰地方や九州で作られていた醤油です。
再仕込み醤油は大豆と小麦、麹を発行させたものに醤油を加えて熟成させているため、色は濃くどろっとした濃厚な味が特徴です。
濃厚な味がつくことから卓上調味料として置いている家庭は多いです。加熱の料理にはあまり使われませんが、刺し身や寿司のつけ醤油として使われます。
白醤油
愛知県三河地域で主に生産されているのが白醤油です。淡口醤油よりもさらに薄くビールのような色合いです。
たまり醤油と逆で小麦が多く使われています。熟成期間を短くしたり、小麦も皮を取り除いたものを使ったり、と色が薄くなるように工夫されています。江戸時代末期から作られ始めた、一番歴史の浅い醤油です。
白醤油は色が薄いことから素材本来の味を活かしたいときに使われます。
スポンサーリンク
適した料理は野菜や炊き込みご飯です。高級料理のかくし味として、またはうどんの汁などに使うことが多いです。
濃口醤油が主流の関東

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主流の醤油種類 | 濃口醤油 |
| 地域 | 関東 |
| 原因 | 塩分抑制、旨味強化、低コスト、地元生産 |
| 発祥地 | 野田(千葉県) |
| 代表的なブランド | キッコーマン |
| 江戸時代の使用されていた醤油 | 上方醤油(関西産、高塩分、高コスト) |
関東では主流の醤油が濃口醤油です。
関東では江戸時代初期は関西の上方醤油を使っていましたが、塩味が強くて旨味が少なく、輸送コストが高くて値段が高くなってしまいました。
江戸の人たちに食べてもらえるように、と塩分を抑えて旨味を引き立てた濃口醤油は発明され、関東で作られているコストもかからず味も江戸好み、値段も安いという濃口醤油は関東の主流となりました。
関東の濃口醤油が発明されたのは野田でした。千葉県野田市のキッコーマン醤油は、今もなお醤油の一大ブランドです。
関西で生まれた淡口醤油

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主流の醤油種類 | 淡口醤油 |
| 地域 | 関西 |
| 原因 | 地元発祥、独自の文化 |
| 発祥地 | 関西 |
| 代表的なブランド | ヒガシマル醤油(うどんスープで有名) |
| 塩分の誤解 | 色が淡いため塩分が少ないと思われがち、実際は多い |
関西では淡口醤油主流です。
淡口醤油は関西が発祥地だと言われています。関東では濃口醤油が爆発的に普及しましたが、関西では依然として上方醤油(淡口醤油)を使い続けていたようです。
淡口という名前ですし実際に色も淡いために塩分が少ないと思っている人も多いですが、実際の塩分は濃口醤油よりも少し高いです。
関西の醤油メーカーでもっとも知られているのが、うどんスープで有名なヒガシマル醤油です。
地域で異なる醤油の好み

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地域ごとの醤油の好み | 地域によって異なる |
| 原因 | 輸送手段の未発達、郷土料理との相互作用 |
| 醤油メーカー数 | かつては10000社、現在は1500社 |
| 関東 | 主に濃口醤油、料理の種類による使い分けなし |
| 関西 | 主に淡口醤油、料理によって濃口醤油も使う |
| 愛知県 | たまり醤油と白醤油の両方を製造、料理による使い分け |
| 九州・山陰・四国 | 主に甘い醤油 |
| 四国の地域差 | 東側(香川、徳島)は淡口醤油、西側(愛媛、高知)は甘い醤油 |
| 愛媛県の瀬戸内海側 | 広島、山口の影響で再仕込み醤油が好まれる |
関東と関西だけでなく、日本全国で見ますと地域で醤油の好みが違うことがわかります。
昔の日本では今のように輸送手段が発達していませんでしたから、地方で製造した醤油に合う郷土料理が根付き、地域ごとに醤油の好みが違ってきたようです。
醤油メーカーはかつては10000社を超えていましたが、現在は1500社ほどで地域色のある醤油メーカーが残っています。
関東では料理の種類によって種類を変えるということなく、どの料理をつくるときも濃口醤油を使います。
関西では淡口醤油が好まれていますが、料理の種類によって濃口醤油を使うなど、使い分けをしている家庭が多いです。
関東と関西の間にある愛知県ではもっとも濃厚な味のたまり醤油ともっとも薄い風味の白醤油のどちらも作っているという面白い地域です。
お刺身にはたまり醤油、茶碗蒸しには白醤油など、料理によって使い分けをします。
そして九州や山陰地方、四国で好んで使われているのは甘い醤油です。ただし、地域性を細かく見ていくと四国は東と西で醤油の好みが違います。
東側の香川県や徳島県は関西の影響を受けているために淡口醤油が好みですし、西側の愛媛県や高知県は九州の影響を受けているために甘い醤油が好みです。
さらに細かく見ると、愛媛県の瀬戸内海側の地域は、広島県や山口県の影響を受けているため、再仕込み醤油を好む人が多いです。
いろんな醤油を試してみよう
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 醤油の味の違いの体験方法 | 各地の郷土料理を試す |
| 料理と醤油の関係 | 料理の種類によって最適な醤油が違う |
| 旅行と醤油 | 同じ素材でも地域の醤油によって味が変わる |
| 自宅での醤油の使い分けのメリット | 料理の風味が変わり、新たな発見がある |
各地の郷土料理を食べてみると、醤油の味の違いを知ることができます。料理の種類によって一番合う醤油は違います。
旅行に行って郷土料理を食べてみると、醤油の味で同じような素材を使っていても味がずいぶん変わってくることに気がつくはず。
醤油の種類をいくつか取り揃えて、作る料理によって使い分けをするのもいいものですよ?
いつもと同じ料理なのに、醤油を変えただけで濃厚な味になったり、素材の味が引き立ったりと、違う良さが出てきて新たな発見ができますよ。