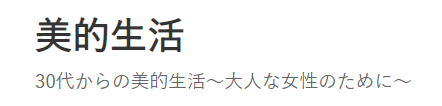甘いものと言えば和菓子と洋菓子がありますが、夏になると食べたくなる和菓子と言えばなんといっても水ようかんという人も多いのではないでしょうか?
ほんのり甘くて冷たくてなんともおいしい水ようかん。夏の暑さも水ようかんを食べると、ちょっと和らぐ感じがしますよね。
水ようかんは自分で買って食べるというだけでなく、夏のお中元、ごあいさつで持っていくお菓子としても定番です。
でも、水ようかんはそもそもどんな食べ物で、羊羹とはどこが違うのでしょうか?
羊羹に「水」という字が前につく水ようかんとはいったいどんな食べ物なのか、夏の定番お菓子の水ようかんについてまとめました。
「水ようかん」と「ようかん」の違い

| 項目 | ようかん(練りようかん) | 水ようかん |
|---|---|---|
| 材料 | 小豆、砂糖、寒天 | 小豆、砂糖、寒天 |
| 製法 | 小豆を炊いた餡と砂糖を練る | 寒天と餡、砂糖を少なめに煮詰めない |
| 水分量 | 普通 | 多い |
| 味 | 濃い | あっさり |
| 食感 | なめらか、しっとり | つるんと、ゼリーのよう |
| 日持ち | 良い | あまり良くない |
ようかんとは練りようかん、水ようかん、そして蒸しようかんのすべてをまとめた総称ですが、一般的にようかんといえば練りようかんのことを指します。
水ようかんとようかん(練りようかん)はまず作り方が違います。
ようかんの材料といえば小豆、砂糖、そして寒天です。水ようかんは材料としてはようかんとほぼ変わらないのですが、ようかんは小豆を炊いた餡と砂糖を練って作ります。
水ようかんは寒天と餡、砂糖を少なめにして煮詰めないで作るため、ようかんよりも水分は多いですし柔らかいです。
水ようかんとようかんは材料は似ていても味が違います。
煮詰めずに砂糖の量も少なめな水ようかんは、しっかりした濃いめの味のようかんと比べて、あっさりしています。
また、食感も水ようかんは水分が多い分だけのど越しが良くつるんとしていてゼリーのような感じです。ようかんはなめらかですが、しっとりしています。
水ようかんとようかんは日持ちも違います。砂糖をたっぷり使って作っているようかんは長期間食べることが出来る保存食でもありますが、水ようかんはあまり日持ちがしません。
水ようかんは冬食べるのもおすすめ
水ようかんは毎年夏になると食べたくはなるけれど、冬の食べ物というイメージはあまりありませんよね。
たしかにのど越しがつるんとしてあっさり味の水ようかんは夏の食べ物としてぴったりですが、冬に食べるのもなかなかいいものです。
夏にしか水ようかんを食べたことがない人も、一度冬の時期にあたたかい部屋の中でぬくぬくしながら、福井の丁稚ようかんを食べてみては?その味が癖になって、やめられなくなるかもしれませんよ。
| 項目 | 夏の水ようかん | 冬の水ようかん |
|---|---|---|
| 一般的なイメージ | 夏の風物詩、暑い日にひんやりと | あまり一般的でない |
| 地域的な特色 | 全国的に人気 | 福井県など一部地域で人気 |
| 用途・場面 | 夏の暑い日に冷たくて食べやすい | 冬にこたつでぬくぬくと |
| 販売場所 | 和菓子屋さん、スーパーなど | 福井では和菓子屋から青果店、洋菓子店まで |
| 歴史的背景 | 現代では夏のお菓子とされる | もともとはお正月のお菓子、冬季に食べられた |
水ようかんとは
この投稿をInstagramで見る
水ようかんは、小豆、寒天、砂糖を使って作ります。口当たりがなめらかでつるっとしていて、しかも冷たく冷やして食べるとおいしい、ということから、夏の風物詩の一つとされています。
スポンサーリンク
水ようかんは夏だけ?
この投稿をInstagramで見る
やわらかい口当たりに、のどを通るとひんやりした味わい、一般的に水ようかんは夏に食べるものというイメージがありますよね。
でも、実は水ようかんはもともと夏だけの食べ物ではなく、冬のお菓子だったのです。
どうして?と思う人もいらっしゃるかもしれませんが、水ようかんはもともとおせち料理の中に入れるデザートとしてお正月だけに作られたと言います。
昔は今のように冷蔵庫がありませんでしたから、日持ちのしない水ようかんは冬の寒い時期に食べるしかなかったのかも。
今は夏食べる人が多い水ようかんですが、京都や福井、石川、山形などの一部の地域では水ようかんを冬のお菓子として食べています。
水ようかんを冬に食べるという地域の中でも、県全体で水ようかんを冬に食べているのが福井県です。
福井県では、冬の時期が来ると、和菓子屋さんだけでなく、青果店や洋菓子店でも水ようかんを売るようになります。
水ようかんを夏の時期にしか食べない地域に住んでいる人にとっては聞いてびっくりしてしまうかもしれませんが、福井県民にとっては、冬の寒い時期に、こたつに入ってぬくぬくしながら冷やした水ようかんを食べるのが普通なのだそうです。
丁稚羊羹とは
この投稿をInstagramで見る
| 項目 | 福井の丁稚羊羹(水ようかん) | 近江八幡の丁稚羊羹 |
|---|---|---|
| 名称の由来 | 丁稚が気軽に買える羊羹、奉公先の改良 | 名称の由来は明確でない |
| 主な材料 | 砂糖、あん、寒天 | 小麦粉、小豆 |
| 作り方 | 寒天で固める | 竹の皮に包んで蒸し上げる |
| 特徴 | 甘さ控えめ、のどごし良い | もちもちした食感 |
| 食べ方 | そのまま食べる | 竹の皮ごと切って食べる |
| 香り | 無し | 竹の香りがする |
| 追加オプション | なし | 栗を入れたものもある |
| 筋模様 | なし | 竹皮の筋模様がつく |
福井県で冬に食べられている水ようかんは、別名で丁稚羊羹と呼ばれています。どうして丁稚羊羹と呼ばれるようになったのか、それにはいくつかの説があります。
一つ目の説が、京都に奉公に来ていた丁稚に福井県に里帰りをするときに、丁稚でも買える気軽な羊羹ということで、水ようかんを持たせたということから広まったというものです。
そして二つの目の説は、奉公先の練り羊羹を改良して、鍋の羊羹に水を混ぜて水羊羹のようにして食べたのが始まりだ、というものです。
福井の水ようかんは、砂糖とあんを寒天で固めたもの。作り方は一般的な水ようかんと同じですが、甘さ控えめでのどごしがよいことが特徴です。
これに対し、近江八幡では丁稚羊羹といえば、小麦粉と小豆を練ったものを、竹の皮に包んでから蒸しあげて作る蒸し羊羹を指します。
もちもちした食感が特徴で、店舗によって栗を入れたものもあり、食べ比べてみるのもおすすめです。
食べるときは羊羹を包んでいる竹の皮ごと切って食べると、手を汚すことなく食べることが出来ます。
竹の皮に包まれているため、丁稚羊羹は竹の香りがほのかに香り、竹の皮をはずすと竹皮の筋模様がついていることも特徴です。