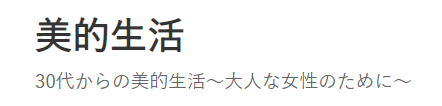おせち料理には切り身から魚介類までさまざまな魚料理が入っています。普段はあまり食べないちょっと贅沢な食材もあって、楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。
おせち料理に込められた意味を知れば、いつもの料理もひと味違って感じられるかも知れませんね。おせち料理に入っている魚料理の種類、それぞれの食べ方や意味、由来についてまとめました。
おせち料理に欠かせない魚

| カテゴリ | 昔の状況 | 現在の状況 |
|---|---|---|
| 基本の食事構成 | 一汁一菜、野菜中心 | 野菜、肉、魚、多様な調理法 |
| 冷蔵・冷凍技術 | なし | あり、発達している |
| 輸送手段 | 未発達 | 発達している |
| 魚の入手可能性 | 漁村や大都市でしか手に入らない | 幅広い地域で手に入る |
| 魚料理の頻度 | 祭りや年越しの特別な時 | 普段の食事でも |
| おせち料理 | 魚料理はご馳走 | 野菜料理と魚料理の詰め合わせ |
おせち料理は重箱の中に野菜料理と魚料理を詰め合わせたものです。
現在では普段の食事でも野菜や肉、魚などを和洋中さまざまな調理法で楽しんでいますが、昔の食生活は一汁一菜が基本で、普段は野菜を中心にした質素の食事がほとんどでした。
今と違って昔は冷蔵、冷凍技術がありませんし、輸送手段も発達していなかったため、魚がすぐに手に入る漁村や、江戸・大阪などの大都市でなければ簡単に魚が手に入りません。
魚料理は祭りや年越しのときにだけ登場するご馳走だったのです。
東は鮭、西はブリ!年取り魚とは?

| カテゴリ | 詳細 |
|---|---|
| 年取り魚の意味 | 大晦日に食べる特別な魚料理 |
| 別名 | 正月魚(しょうがつうお) |
| 東日本の年取り魚 | 鮭 |
| 西日本の年取り魚 | ブリ |
| 東西の境界 | 糸魚川 |
| 長野県の特例 | 長野市は鮭、松本市はブリ |
| 共通点 | 塩蔵による輸送が可能 |
| 年取り魚の条件 | 塩蔵で長期保存、遠距離輸送が可能 |
大晦日に食べる膳には、「年取り魚」といって特別に魚料理がつくのが習わしでした。年取り魚は正月に食べることから「正月魚(しょうがつうお)」と呼ぶ地域もあります。
年取り魚は東と西で種類が違い、東日本では「鮭」、西日本では「ブリ」を食べます。東西の境目は糸魚川にあり、境界線上にある長野県では、東側にある長野市では鮭、西側にある松本市はブリを食べるそうです。
鮭とブリはどちらも塩蔵による輸送が可能と言う共通点があります。塩蔵による長期保存が可能で遠いところまで運べることが、年取り魚の条件だと言えるでしょう。
おせちに入っている魚料理の意味・由来

| 魚料理 | 調理方法 | 意味・由来 |
|---|---|---|
| ブリ | 照り焼き | 立身出世、出世魚 |
| 鮭 | 昆布巻き | 不老長寿、家族の健康と幸せ |
| 鯛 | 塩焼き | めでたい、新しい年を祝う |
| 田作り | 甘露煮 | 五穀豊穣 |
| 数の子 | 塩漬け | 子宝と子孫繁栄 |
| 海老 | 塩焼き/旨煮 | 不老長寿、見た目の豪華さ |
| なまこ | 酢漬け | 豊作 |
ブリ
ブリは照り焼きにして、第二のお重に詰めます。ブリには「出世しますように」と立身出世の願いが込められています。
ブリは出世魚として知られており、最初はワカシ(ツバス)、続いてイナダ(ハマチ)、ワラサ(メジロ)、そして最後にブリへと呼び名が変わります。
ワカシのころは20cmほどだったブリは、ブリと呼ばれる頃には1mにまで成長するそうです。
鮭(昆布巻き)
鮭は昆布巻きにして食べることが多いです。
昆布巻きは、鮭だけでなくニシンやシシャモ、サバ、タラコをいれることもあります。昆布巻きは「養老昆布(よろこぶ)」と書き、不老長寿を意味します。
また、欣ぶという意味から、家族みんなが健やかに顔を合わせられますように、という幸せを願う気持ちが込められています。
スポンサーリンク
鯛
結婚式などおめでたい席に登場することが多い鯛は、塩焼きにしておせち料理のブリと同じく第二のお重の中に入れます。
鯛は「めでたい」と言われるおめでたい魚の代表です。七福神の恵比寿さまが持つ魚でもある鯛は、新しい年を祝う料理として欠かせません。
田作り
田作りは別名、ごまめとも呼ばれています。カタクチイワシの稚魚を乾煎りしてから、醤油やみりん、砂糖を煮詰めたものにからめて甘露煮にしたもので、重箱の一番上の段に入れます。
魚なのに田作りと呼ばれるのは、原料であるカタクチイワシが畑の肥料として使われるものだからです。肥料の原料はいくつか種類がありますが、イワシを肥料にすると豊作になることが多いと言われます。豊作を呼ぶカタクチイワシを使っているところから、田作りには五穀豊穣の願いが込められています。
数の子
数の子はニシンの卵で、鮮度を守るために塩漬けにして売られています。数の子はそのままでは塩が強すぎるため、塩抜きをしてから食べます。
塩を抜きすぎると本来の味・食感が失われ、塩味がまだ強いと辛すぎるので、塩の抜き加減が非常に重要な食材です。
魚の卵は数え切れないぐらいたくさん数がありますよね。数の子はニシンの卵であることから二親(ニシン)の卵、と考えられ、子宝と子孫繁栄を願う気持ちが込められています。
海老
海老はシンプルに頭を付けたまま塩焼きにして食べたり、だし汁で煮て旨煮にして食べたりします。
料理に一つ海老が入っていると、見た目にもかなり豪華になりますよね。おせち料理も海老があるとないでは全然見た目が変わります。
海老には長いひげついていますが、ひげは老人をイメージさせます。煮たり炒めたりすることで腰が曲がることから、腰が曲がるまで長生きしますように、という不老長寿の願いが込められています。
なまこ(酢漬け)
なまこは酢漬けにしてなまこ酢として食べます。
なまこは俵のような形をしていますよね。そのことから、なまこは俵子とも呼ばれています。俵といえば米俵ですから、なまこには豊作への願いが込められています。
魚は意味を考えながら味わって食べよう

| メッセージ | 詳細 |
|---|---|
| おせちの食材 | 家族の健康や幸せを願う縁起のよいものが多い |
| 普段の食事との違い | お正月に特有の魚料理が多く、珍しい食材も楽しめる |
| 特に注目するべき魚料理 | 数の子、田作りなど、普段めったに食べないもの |
| お勧めする過ごし方 | おせち料理の意味を理解しながら新年を過ごす |
おせち料理の食材は、家族の健康や幸せを願う縁起のよいものが多いです。
普段の食卓ではお肉が多いご家庭でも、おせちの魚料理は特別。お正月以外、めったに食べない数の子や田作りは、楽しみにしている方も多いでしょう。
今年のお正月は、おせち料理に込められた意味を考えながら過ごしてみるのもよさそうです。