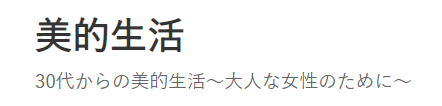このページの目次
沖縄の正月料理はとっても個性的!
| 項目 | 沖縄の正月料理 | 本土の正月料理 |
|---|---|---|
| 文化的背景 | 琉球王国、中国の影響 | 日本本土の歴史と文化 |
| 地理・気候 | 亜熱帯 | 温帯 |
| 主な食材 | 豚肉など | 魚、海鮮、野菜など |
| 料理の特徴 | 独自の調理法と食材 | おせち料理、お雑煮 |
| 味わい | 沖縄独特の風味 | 本土独特の風味 |
| 正月料理のイメージの変化 | 一変する | 定番 |
正月料理と言えばおせち料理にお雑煮が定番ですよね。でも、沖縄で食べる正月料理はかなり違っています。
沖縄は古くは琉球王国として、中国の強い影響を受けながら独自の文化が発展してきました。
亜熱帯に属することから、食材や調理法も本土とは違います。そのため、普段の食べ物も日本の他の地域と異なる雰囲気のものが多いのが特徴です。
沖縄で食べる正月料理は、沖縄ならではの豚肉を使ったものなどいろいろな種類があります。
本土のおせち料理とは全く違っていますがどれも本当に美味しく、正月料理のイメージが一変すること請け合いです。
沖縄ではどんな正月料理を食べているのか、沖縄でしか味わえない正月料理を紹介します。
沖縄ではおせち料理は食べない!?
沖縄にはいわゆる「おせち料理」はありません。
ご先祖さまを大切にする沖縄では、お正月に限らず法事、お盆、お彼岸などの行事に特別な料理を用意する習慣があります。
沖縄のお正月料理の特徴を見て行きましょう。
沖縄ではおせち料理の代わりに重箱料理が振る舞われる
お彼岸、本土ではお墓参り、こちらではお仏壇にお供え物をして、うーとーとぅ(拝む)する。スーパーではおはぎも売っているけど、食べないし、こんな料理を大皿に盛ってお供えし、親族が集まり、おしゃべりの花が咲きます。 #御三味(ウサンミ) pic.twitter.com/l3gDXd7rBo
? 敬子 (@tamikeiko) 2016年3月21日
| 項目 | 沖縄の御三味 | 本土のおせち料理 |
|---|---|---|
| お祝いの場合 | 親戚一同が集まる時 | 正月 |
| 料理の形式 | 重箱料理 | おせち料理 |
| 名称 | 御三味(うさんみ) | おせち料理 |
| 料理の種類 | 7種類から9種類 | 多様 |
| 地域性 | 沖縄独特 | 本土独特 |
| イベントとの連携 | 正月以外も振る舞われる | 主に正月 |
| 関連する習慣 | うーとーとぅ(拝む) | お墓参り |
お正月になると親戚一同が集まることが多いというのは、沖縄も日本の他の地域と同様です。
しかし、その時に振る舞われる料理が沖縄と他の地域では違うのです。沖縄で振る舞われるものはおせち料理ではなく重箱料理です。その名前も御三味(うさんみ)といいます。
御三味と言われてもピンとこない人が多いかも知れませんね。御三味はお正月に食べるものと決まっているわけではありません。
沖縄ではお祝いのときなど親戚一同が集まった時に、御三味が振る舞われます。御三味の中には7種類から9種類のものが入っています。
本土で食べるおせち料理とは内容が全く違っていますので、入っている料理については後ほどご紹介しますね。
沖縄ではお雑煮も食べない
| 項目 | 沖縄の汁物 | 本土の汁物 |
|---|---|---|
| 一般的な名前 | 中身汁、イナムドゥチ | お雑煮 |
| 主な食材 | 豚の内臓(モツ) | 魚、野菜、もち |
| 出汁 | 鰹節の出汁 | 一般に鶏ガラ、昆布など |
| 習慣の起源 | 沖縄独特 | 本土独特 |
| 現在の状況 | 人気料理、スーパーでも販売 | 定番料理 |
| 歯ごたえ・食感 | あり | 一般にはなし |
| 手間 | 手間がかかる | 一般に手間がかかる |
| 最近の変化 | 本土からの移住者によりお雑煮も増加 | 変わらず定番 |
お正月にはおせちと並んで必ず食べると言う人の多いお雑煮。おせち料理を食べない沖縄では、どうなのか気になりますよね。
沖縄にはもともとお雑煮を食べる習慣はありませんでした。しかし、最近では本土からの移住者が増えていることを背景に、お雑煮を作るご家庭も多くなっています。
お雑煮の代わりに沖縄で古くから親しまれて来たのが中身汁やイナムドゥチといった汁物です。中身汁とは豚の内臓、つまりモツを煮込んだ鰹節の出汁で作ったスープです。
中身汁にはモツの中でも豚の小腸や胃の部分が使われ、歯ごたえや食感があって味わいがあります。
作るのに手間がかかることから、スーパーで下処理されたモツやレトルトが売られているほどの人気料理です。
もう一つのイナムドゥチは沢山の具が入った豪華な汁物です。
中に入っている具は、細く短冊切りした豚の三枚肉にコンニャク、かまぼこ、しいたけ、油揚げなど。味付けは九州地方の特産である甘みのある白味噌です。
沖縄料理はお出汁の旨味を活かした「あじくーたー」(味が濃厚)な味付けが特徴。塩分などは意外に控えめです。
そのため、甘みのある白味噌を使うイナムドゥチは、沖縄では好きな人と嫌いな人に分かれるようですよ。
沖縄の正月料理の種類と特徴

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 御三味の基本 | 海・天・地の食材を用いる |
| 御三味の由来 | 中国の影響、神様への供え物として |
| 重箱の形 | 正方形で四段重ねが基本 |
| 重箱の内容 | 基本9品、地域により違いあり |
| お餅の扱い | 「餅重(ムチジュウ)」に詰める、料理と一緒に詰めない |
| お餅の数 | 9個または15個など、縁起の良い奇数 |
| 2で割り切れる数について | 縁起が悪いとされる |
| 鏡餅について | 最近は増えているが、本来は沖縄にはなかった |
| 本土文化の影響 | 本土に復帰後、他の地域の風習も伝わってきた |
海・天・地の食を使う
沖縄ならではの正月料理である御三味は、海・天・地の食を使って作ることが決められています。
海・天・地の食が使われるようになったのは、中国からの言い伝えによるものです。日本の他の地域も同じですが、正月料理は神様のお供えとして作りますよね。
それと同じく、沖縄の御三味も、中国で神仏へのお供え物として使われていた、海・天・地の食材が使われています。
正方形の重箱に詰める
沖縄の正月料理は正方形の重箱に詰めるのが決まりとなっています。重箱にもいろいろな種類がありますが、もっとも基本的な形は四段重ねのものです。
二段を白餅を入れるために使い、それ以外の二段の中にカステラかまぼこや紅白かまぼこ、揚げ豆腐や天ぷら、田芋、昆布、ゴボウ、こんにゃく、皮付きの豚の三枚肉などをきれいに並べて詰めていきます。
基本は9品。
御三味の基本は9品です。カステラかまぼこに紅白かまぼこ、揚げ豆腐、天ぷら、田芋、昆布、ごぼう、こんにゃくそして皮付きの豚の三枚肉という9品が重箱の中に入っています。
重箱に詰める料理の内容については、地域によって多少違いがあります。
お餅は餅重(ムチジュウ)に別に詰める
お正月と言えば欠かせないのが「お餅」ですよね。沖縄ではお餅は「餅重」(ムチジュウ)と呼ばれるお餅専用の重箱に詰めます。お餅と料理を一緒に詰めるのはNGです。
お餅の数にも決まりがあり、9個または15個など縁起の良い数を重箱に詰めます。
沖縄では2で割り切れる数は縁起が悪いとされていますので、2で割り切れない数字である奇数の数だけ白餅は必要です。
沖縄には鏡餅を飾る習慣はありませんでしたが、最近は沖縄でも鏡餅を飾る人が増えています。
本土に復帰してから日本の他の地域の風習が沖縄にも伝わったからだそうです。
沖縄ではおせちより「オードブル」が人気
沖縄の正月が独特すぎて他県の正月を感じてみたいと思った。(食べ物)
まずおせち料理食べた事ない。沖縄はオードブルか重箱のやつ。あとお雑煮もない。→ 中身汁! pic.twitter.com/3IatEcxOVx
? yuya (@yuya_wo) 2017年1月9日
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 伝統的な正月料理 | 重箱料理、御三味、中身汁等 |
| 重箱料理の頻度 | 年に一度以上、作る負担が大きい |
| 最近の傾向 | オードブルが人気、手軽にお店で購入可能 |
| オードブルの一般的な意味 | シュリンプ、カナッペ、マリネ、スモークサーモン等の前菜 |
| 沖縄のオードブル内容 | 三枚肉の煮付け、揚げ物等のおかず主体 |
| その他 | 唐揚げや肉団子など、子供の好きなものも含まれる |
おせち料理って年に一度とは言え、作るのは大変ですし、毎年同じだとやはり飽きてしまうこともありますよね。
沖縄の重箱料理は年に一度ではなくもっとですので、作る方の負担も大きいようです。
そのためか、最近の沖縄では御三味を家で手作りして用意するよりも手軽にお店で手に入るオードブルを求める人が増えてきました。
以前は行事のたびに手作りの重箱料理を用意することが定番でしたが、ライフスタイルの変化からスーパーやお弁当屋さんでオードブルを注文するご家庭が多くなっています。
オードブルと聞くとシュリンプ、カナッペ、マリネ、スモークサーモンなどコース料理の最初に出される軽めの前菜が思い浮かびますが、沖縄のオードブルは内容がちょっと違います。
沖縄のオードブルに入っているものは、三枚肉の煮付けなどの肉料理、または揚げ物が主です。
前菜とというよりもしっかりしたおかずが多く入っている沖縄のオードブルならば、お正月には他に何か料理を用意しなくてもお腹がいっぱいになりそうです。
唐揚げや肉団子など、子供の好きそうなものもオードブルの中には含まれていますよ。
「オードブル」は沖縄のお正月の新習慣!?
沖縄では正月におせちではなく、オードブルがでる家庭が多い!!
うちなーんちゅのみなさん、これあるあるですか ^ ^?
#沖縄正月あるある pic.twitter.com/cvJJmikpgj? おきなわLikes (@okinawa_likes) 2017年1月4日
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 大家族の影響 | 沖縄には大家族が多いため、正月に多くの人が集まる |
| 若者の働きぶり | 若い人が働いていることが多く、高齢者だけでの料理準備は大変 |
| オードブルの普及 | スーパーやお弁当屋で手軽に購入でき、家族全員が好きな料理 |
| おせちとの違い | 最近通販でおせちを購入する家庭も増えているが、抵抗感もある |
| オードブルの定着 | 手軽で美味しいオードブルが、新たな正月の習慣として定着しつつある |
沖縄は大家族が多いですから、正月にはかなりの人数が一つのところに集まります。
若い人は働きに出ていることが多く、みんなが食べる料理をおじいちゃん、おばあちゃんだけで用意するのは大変です。
そのため、お正月をみんなで楽しくむかえるために、子供からおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが好きなオードブルをスーパーやお弁当やさんで買ってくるのが定番になりつつあります。
最近では通販などでおせちを買うご家庭も増えていますよね。
抵抗のある方も少なくないようですが、手軽に用意できて美味しく食べれるオードブルは、正月の一つの習慣として定着しつつあるようです。