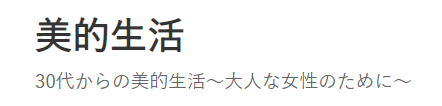子供も大人も好きな人が多くて、日本では今や国民食のカレー。一週間に1回はカレーを食べているという家庭も多いのではないでしょうか。
市販のカレールーを使って作る方、こだわりがあってカレー粉をいろいろかけあわせて作る方、カレーの作り方は人それぞれですが、日本のカレーにはシャバシャバしたカレーとどろどろのカレーがあって、人によって好みが分かれています。
日本のカレーといえばどろっとしたカレーが多いですが、海外のカレーはシャバシャバしたものが主流です。
日本のドロッとしたカレーはどこから入ったものなのでしょうか?
日本に入ってカレーは色々な形に進化していますが、その進化したカレーにはどんなものがある?日本の家庭にはなくてはならない定番の料理、カレーについてまとめました。
そもそもカレーって

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 語源 | インド料理の一つ、英語のCurryより。Kari(タミール語でソース)またはTurcarri(ヒンズー語で誇り高い/おいしいもの)が由来。 |
| インドでの種類 | 地方によって異なる、肉類中心のカレー、魚介類や野菜のカレーなど。香り、色、辛さも地域や好みにより多様。 |
カレーはもともとインド料理の一つです。カレーの語源は、香辛料(スパイス)で具材を煮込んだ汁状のものを指す英語のCurryから来ています。
カレーという名前の由来は、インドのタミール語でソースを意味するKari(カリ)から来たものではないか、という説と、
ヒンズー語で誇り高いもの、おいしいものを指すTurcarri(ターカリー)からTurri(ターリ)そしてカレーになったという説もあります。
インドではいろいろな種類のカレーが存在します。地方によって肉類を中心にしたカレー、または魚介類や野菜だけのカレーもありますし、香りや色や辛みも、それぞれ好みによって違います。
北部のカレーとは?
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| ベース | 牛乳や生クリームを使用し濃厚な味わい |
| スパイス | ガラムマサラ、クミン、カルダモン、ターメリック |
| 合わせる食べ物 | チャパティ、パラタ、ナン |
| 代表的なメニュー | キーマカレー、バターチキンカレー、マトンカレー |
インド北部のカレーは牛乳や生クリームを使っていて濃厚なのが特徴です。
使われるスパイスはミックススパイスであるガラムマサラ、そのほかにクミン、カルダモン、ターメリックも使われます。
北部のカレーは小麦粉をこねて焼いて作ったチャパティやパラタ、ナンなどにつけて食べます。
キーマカレー、バターチキンカレー、マトンカレーなど、北部のカレーは肉を使ったメニューが多く存在します。
南部のカレーとは?
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| テクスチャ | 水分が多くシャバシャバした構造 |
| スパイス | マスタードシード、レッドペッパー、カレーリーフ、ココナッツミルク、タマリンド |
| 合わせる食べ物 | ご飯 |
| 主な材料 | 野菜や豆 |
北部よりも暑い南部の地域のカレーは水分が多くてシャバシャバしていることが特徴です。
スパイスは、マスタードシードにレッドペッパー、カレーリーフ、ココナッツミルクや酸味のあるフルーツのタマリンドなどが使われます。
南部のカレーはご飯にかけて食べます。野菜や豆を使ったカレーが多いです。
日本のカレーどろっとしてる理由

| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| どろっとした理由 | 小麦粉が入ったカレールーによるとろみ |
| 起源 | イギリスから伝わった。イギリス海軍がシチュー代わりとして考案 |
| インドとの違い | インドではシャバシャバ、イギリス経由でどろっとしたカレーが日本に伝来 |
| 明治時代の影響 | イギリス文明の取り入れと共にカレーも伝来 |
日本のカレーはどうしてどろっとしているのかと言えば、カレールーに入れられている小麦粉のとろみから来ています。
カレーのおおもとであるインドではシャバシャバしたカレーが多いのにどうして日本のカレーには小麦粉が入ったのか、それは日本のカレーがイギリスから来たためです。
インドで古くから食べられてきたカレーは、インドがイギリスの植民地になったことによりイギリスに伝えられました。
当時伝えられたカレーはインド南部のシャバシャバしたカレーでしたが、そのカレーをもとにどろっとしたカレーを考えたのがイギリス海軍でした。
スポンサーリンク
イギリス海軍の船員たちは、シチューを食べたいけれど牛乳が日持ちがしなくて手に入らないから食べれない、シチューに代わるものはないか、と具材がよく似ていて手軽に作れる小麦粉を入れたカレールウを使ったカレーを食べるようになったそうです。
日本は明治時代にイギリスから色々な文明を取り入れたことから、カレーもイギリス海軍が考えたどろっとしたカレーが伝えられ、今に至ります。
イギリスから取り入れたカレールゥがもとになっているので日本のカレーはどろっとしているんですね。
進化系?カレーが登場

インドからイギリスを経由して日本に入ってきたカレーは日本に入って進化し、さまざまなカレーが登場しました。
カツカレー
| 起源説 | 説明 |
|---|---|
| 浅草『河金』起源説 | カツをキャベツと一緒にご飯の上にのせ、カレーをかけた『河金丼』がカツカレーの始まり |
| 新宿『王ろじ』起源説 | フレンチ出身の初代シェフ考案の「とん丼」が元になった可能性 |
| 千葉繁氏起源説 | 元巨人軍千葉繁氏のアイデアでカツとカレーライスを組み合わせた説 |
| 神保町『キッチン南海』起源説 | 黒いカレーにカツとキャベツを添えたスタイルが始まりとの説 |
カツカレーのカツは、たっぷりの油で揚げてキャベツの千切りを添えたポークカツレツが始まりでした。
このカツとカレーを合わせてカツカレーを作った始まりは、浅草『河金』ではないかと言われています。
浅草『河金』では、お客様の要望にこたえて、ご飯の上にキャベツと豚もも肉のカツをのせて、その上にカレーをかけた『河金丼』を売り出しました。それがカツカレーの始まりではないかと言われています。
そのほかの説としてはフレンチで修行していた初代シェフがオリジナルメニューとして考えた新宿の『王ろじ』が売り出した「とん丼」から来たというもの、元巨人軍の故千葉繁氏のアイデアでカツレツとカレーライスを一つの皿にのせたカツカレー、
さらに黒いカレーにカツ、横にキャベツを添えた『神保町 キッチン南海』の元祖カツカレーがカツカレーの始まりではないかという説もあります。
カレーうどん
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 起源説 | 東京早稲田の三朝庵、または目黒の朝松庵が発祥の地とされる |
| 背景 | 洋食が日本に伝わり人気を博す中で和食店の経営が厳しくなり、新たなメニューを模索 |
| 和洋折衷 | 洋食のカレーと和食のうどんを組み合わせたカレーうどんが考案され、提供されるようになった |
カレーうどんの始まりは東京早稲田の三朝庵、または目黒の朝松庵ではないかと言われています。
洋食が日本に伝えられてから日本人は洋食を好んで食べるようになり、日本に昔からあった和食の店は経営がだんだん厳しくなってきたそうです。
うどん、そば店でも店を続けるためには何か考えなければ、ということで、洋食と和食をかけあわせたカレーうどんが登場したと言われています。
スープカレー
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 起源 | ネパール料理がヒントで、北海道札幌市で開発された薬膳カレーが元になる |
| 開発地 | 北海道札幌市 |
| スパイス | 20種類以上のスパイスを使用、漢方やハーブも配合される |
| 薬膳効果 | 高い薬膳効果とヘルシーな点が特徴 |
| 人気の理由 | 長時間煮込んだチキンがとろとろでおいしいため人気を集める |
スープカレーはネパール料理をヒントにして生まれました。ネパールのカレーから北海道の札幌市で開発された薬膳カレーは改良されて、現在のスープカレーになったそうです。
スープカレーは20種類以上のスパイスを調合してスープを作ります。スパイスの中には漢方やハーブなどが配合されていますから非常に薬膳効果が高く、ヘルシーです。
また時間をかけてじっくり煮込んだチキンはとろとろしていて非常においしいと人気になりました。
焼きカレー
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 構成 | ご飯、カレー、チーズ、卵を使用 |
| 調理方法 | オーブンで焼いて食べる |
| 起源の場所 | 福岡県北九州市の門司港 |
| 発祥の経緯 | 余ったカレーをグラタン風に焼いて評判になる |
焼きカレーはご飯の上にカレー、チーズ、卵などをのせてオーブンで焼いて食べます。焼きカレーが生まれたのは福岡県北九州市の門司港。
門司港の喫茶店では、余ったカレーをグラタン風に焼いてみたらおいしかったので焼きカレーとしてお店に出すようになったと言います。
進化するカレーを楽しもう
インドで生まれて、イギリスから日本に伝わり、現在ではいろいろ進化を遂げた日本のカレー。ちょっと食べていないと食べたくなる、日本では定番のメニューですよね。
ご飯にかけて食べるカレーはもちろん、今ではナンにつけて食べるカレーも、カツカレーやカレーうどん、スープカレーや焼きカレーも人気です。今後も新たに、進化系のカレーが日本から生み出されるのが楽しみですね。