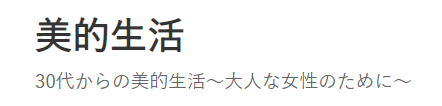同じ日本でありながら、関東と関西は味の好みがずいぶん違いますよね。
関東の人は香りが強くてしっかりした味付けのものが好きですし、関西の人はまろやかな甘味があるあっさりした味付けのものを好みます。
昔から江戸の武士たちは味が濃いものが好きでしたし、関西は公家の上品な伝統食や上方商人のさっぱりした味が好みでした。
そんな歴史的に味の好みが違う関東と関西ですが、同じ食べ物であっても呼び方が違うものが存在します。
関東と関西で呼び方の違う食べ物にはどんな物があるのか、まとめました。
関西と関東で呼び方の違う食べ物

食材から麺類、お菓子まで、関西と関東で呼び方の違う食べ物はいくつもあります。
大判焼き 関西は回転焼、関東は今川焼
| 関東 | 関西 | 全国 | |
|---|---|---|---|
| 呼び名 | 今川焼き | 回転焼き | 大判焼き |
| 名前の由来 | 神田今川橋付近の店が名前をつけた | 型を回転させて焼くことから | 関東と関西など全国的に通じる名前 |
大判焼きとは、小麦粉に卵と砂糖を入れて水で溶いた生地を型に流しこみ、その中に小豆あんなどいろいろなあんを入れて焼き上げて作るものものです。
全国的には「大判焼き」といえば通じるこの食べ物は、関東と関西ではそれぞれ別の呼び方をします。
関東の呼び方は「今川焼き」。これは江戸時代にこの大判焼きを売り出した店が神田今川橋付近で、この地名をとって「今川焼き」という名前で売り出したことが始まりのようです。
かたや、関西での呼び名は回転焼きです。大判焼きは円形の焼型に入れて焼きますが、型を回転させて焼くことからその名前がつけられました。関西の他、九州でも回転焼きと呼んでいます。
イカ焼き

| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 呼び名 | イカ焼き | イカ焼き |
| 特徴 | イカを丸ごと焼いたもの | ゲソの入った薄いお好み焼き |
| 関西での別名 | – | 姿焼き |
関東のイカ焼きはイカを丸ごと焼いたものですが、関西のイカ焼きはゲソの入った薄いお好み焼きで、たこ焼き、お好み焼きと並ぶ3大粉もののひとつです。
関西では関東風のイカ焼きは「姿焼き」と言うそうですよ。
きつねとたぬき
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| うどんの具 | 油揚げ、てんかす | 油揚げ、天かす |
| そばの具 | 油揚げ、てんかす | 油揚げ、天かす |
| きつね | きつねうどん | きつねうどん |
| たぬき | たぬきうどん | たぬきそば |
| 揚げ玉の呼び名 | 揚げ玉 | 天かす |
| 揚げ玉をのせたうどんの呼び名 | たぬきうどん | 天かすうどん |
| 揚げ玉をのせたそばの呼び名 | たぬきそば | 天かすそば |
関東では具に油揚げがのっているそばやうどんをきつねと呼び、具にてんかすをのせているそばやうどんをたぬきと呼んでいます。
しかし関西ではたぬきうどんときつねそばは基本的にありません。
関東の人から言えばなぜ?と不思議に感じるでしょうが、関西では油揚げののっているうどんはきつねうどんと呼びますが、油揚げののっているそばはきつねそばではなく、たぬきと呼ぶのです。
では、関西では揚げ玉ののったうどんはないのでしょうか。実は、名前が違うだけで揚げ玉ののったうどんはあります。
関西では揚げ玉のことを天かすと呼んでいるので、揚げ玉をのせたうどんは天かすうどん、揚げ玉をのせたそばは天かすそばと呼んでいます。
おしることぜんざい
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 汁気あり | おしるこ(あんの種類不問) | おしるこ(こしあん)、ぜんざい(つぶあん) |
| 汁気なし | ぜんざい(あんの種類不問) | 亀山 |
| つぶあん | 呼び方を変えない | ぜんざい(汁気あり)、亀山(汁気なし) |
| こしあん | 呼び方を変えない | おしるこ(汁気あり)、亀山(汁気なし) |
あんの中にもちが入っているおしるこやぜんざいも、関東と関西では考え方が違います。
関東では汁気のあるものを「おしるこ」そして汁気のないものを「ぜんざい」と呼びます。あんにはつぶあんとこしあんがありますが、関東ではあんの種類で呼び方を変えていません。
けれど関西では汁気があってこしあんを使っているものを「おしるこ」、汁気があってつぶあんを使っているものを「ぜんざい」と呼びます。汁気のないものについては、関西では「亀山」と呼び、区別しています。
ネギと言えば?

| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| ネギの種類 | 白ネギ | 青ネギ |
| 用途 | 多様(煮物、焼き物など) | 主に薬味 |
| 部分 | 土中で成長する茎の部分 | ネギの葉の部分 |
| 特徴 | 寒さに強い、飛ばされずに栽培可 | 豆腐や鍋のタレに使う |
いろいろな料理で使うネギも、関東と関西では使う部分が違います。
関東から北の地域で使うネギは白ネギです。白ネギとは土の中で成長する茎の部分を指します。
地中に埋まっている部分ですから、白ネギは寒さに強い風が吹いても飛ばされずに栽培できることから、関東では白ネギを栽培し、食べて来ました。
関西で使われているネギは青ネギで、ネギの葉の部分です。青ネギは主に薬味として使われます。
豆腐に添えたりお鍋を食べるときのタレに入れるなどして使う青ネギ、関西ではネギと言えば青のイメージです。
揚げせんべい
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 名前 | 歌舞伎揚げ | ぼんち揚げ |
| 味 | 醤油味 | 甘め |
| 食感 | 普通 | 柔らかい |
| パッケージ | 緑・黒・赤 | 色が控えめ |
| インスピレーション | 歌舞伎 | 山崎豊子の「ぼんち」 |
| 特徴 | 日本の伝統文化と結びつけ | 関西の庶民の味 |
関東で揚げせんべいといえば醤油味の「歌舞伎揚げ」です。
日本の伝統文化である歌舞伎と庶民のお菓子であるせんべいを結びつけた関東の揚げせんべいは、歌舞伎の定式幕である「緑・黒・赤」のパッケージで販売されています。
関西で揚げ煎餅と言えば、歌舞伎揚げに比べると色が控えめ、味も甘め、食感は柔らかく作られた「ぼんち揚げ」です。
大阪の作家である山崎豊子さんの「大阪もの」第3作であるベストセラーの「ぼんち」からヒントを得て名付けられたこの「ぼんち揚げ」はまさに関西の庶民の味です。
お酒のつまみは?
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 名前 | つまみ | アテ |
| 内容物 | 同じ | 同じ |
| 語源 | つまみもの | お酒にあてがう |
お酒にそえる食べ物のことを関東では「つまみ」と呼びますが、関西では「アテ」と呼びます。「アテ」と「つまみ」は同義語で、出てくるものに違いはありません。
アテという言葉の語源は、お酒にあてがうという言葉から来ています。
ちなみにおつまみという言葉は「つまみもの」という言葉が語源となっており、お酒の肴には手でつまんで食べるものが多かったことから名前がつけられたといいます。
由来を考えても、言い方が違うだけで「つまみ」と「アテ」は同じものを表す言葉ですね。
お通し?つきだし?
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 名前 | お通し | つきだし |
| 内容物 | 同じ | 同じ |
| 語源 | 不明 | 先付け |
居酒屋さんに行ったときにまず出てくるものと言えばお通しですが、このお通しという言葉は関東の言葉で、関西では「つきだし」と呼びます。
スポンサーリンク
「お通し」も「つきだし」も同じものですが、「つきだし」という言葉は料理の前に出す「先付け」が由来となっています。
鶏肉はなんて呼ぶ?
| 関東 | 関西・九州・中部一部 | |
|---|---|---|
| 名前 | 鶏肉 | かしわ |
| 現在の種類 | ブロイラー | ブロイラー |
| 歴史的な種類 | 在来種 | 在来種(かしわ) |
| 語源 | 不明 | 柏の葉に似た羽色 |
鶏肉のことを関東では普通に鶏肉と呼んでいますが、関西地方や九州地方、そして中部地方の一部では「かしわ」と呼んでいます。
現在、鶏肉はアメリカ発祥の食肉用の白いニワトリの肉であるブロイラーがほとんどですが、日本ではブロイラーを導入するまでは茶褐色の在来種のニワトリの肉を食べてきました。
その在来種のニワトリは羽が柏の葉の色に似ていることから「かしわ」と呼ばれていました。
ブロイラーが鶏肉として食べられるようになってからは在来種である「かしわ」はあまり使われなくなったのですが、
鶏肉を「かしわ」と呼んでいたその呼び方だけが関西では残っていて、鶏肉を「かしわ」と今でも呼んでいるようです。
豚まんと肉まん

| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 名前 | 肉まん | 豚まん |
| 内容物 | 豚肉 | 豚肉 |
| 特徴 | 豚肉が一般的 | 豚肉を明示 |
| 地域の肉 | 特になし | 松坂牛、神戸牛 |
| 語源の理由 | 一般的な呼び方 | 豚肉が入っていることを明示 |
豚肉が入ったおまんじゅうのことを関東の人は肉まんと呼びますが、関西では豚まんと呼びます。
関西では松坂や神戸など有名な牛肉の産地がありますし、肉と言われると牛肉を想像してしまうことが多いです。
ですから、肉まんと聞くと牛肉の入ったお饅頭が想像されてしまうため、豚肉が入っているおまんじゅうであることをはっきり示すために「豚まん」と呼んでいます。
マクドナルドの呼び方
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 呼び名 | マック | マクド |
| 見解 | 正解 | 正解 |
マクドナルドのことを関東では「マック」と呼んでいますが、関西では「マクド」と呼んでいます。
正しい呼び方としてはマクドナルドなのですが、日本マクドナルドと呼ぶのはちょっと長い、そんな思いから日本ではマクドナルドのことを略称で呼んでいるのですが、
関東では「マック」関西では「マクド」と呼び方は2つにはっきり分かれています。
マックとマクドのどちらが略称として正しいの?と気になりますが、マクドナルドの見解によれば、マックであろうとマクドであろうと良いらしいです。
親しみを込めて呼んでいるわけですから、マクドナルドにとってはどちらの呼び方も正解なのでしょう。
おでん:関西では関東煮(かんとだき)
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 呼び名 | おでん | 関東炊き |
| 特徴 | 茶色が濃く、だしとしょうゆがしっかり染み込む | 甘くてまろやか、薄味 |
| 由来 | 関東から伝来 | 関東からの料理を関西風にアレンジ |
おでんは関東にも関西にもありますが、関西ではおでんのことを「関東炊き(かんとだき)」と呼んでいます。
おでんの作り方は関東と関西で特に違いはありません。
関東から伝来したものですから関東の名をそのまま使っておでんは関西の人にとっては「関東炊き」なのですが、味付けは関東風ではなく関西らしいものとなっています。
関西の「関東炊き」はだしとしょうゆがしっかり染み込んだ茶色が濃いおでんに比べ、甘くまろやかで薄味が特徴です。
おにぎりとおむすび
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 呼び名 | おにぎり | おむすび |
| 特徴 | 握り飯、ぎゅうぎゅうに握ってつめこんだもの | 平安時代の貴族の女性たちが使っていた呼び方 |
| 由来 | 不明 | 古事記に出てくる「むすびのかみ」から |
おにぎりのことをおむすびと呼ぶ人もいますよね。家庭によって呼び方も変わりますが、関東ではおにぎり、関西ではおむすびと呼ぶことが多いです。
おにぎりとおむすびの呼び方の違いはどこから生まれたかについては諸説あって、どれが正しいかは定かではありません。
しかし、おにぎりといえば握り飯、ぎゅうぎゅうに握ってつめこんだものというイメージです。
その反対におむすびといえば平安時代の貴族の女性たちの呼び方で、日本の歴史書である古事記に出てくる「むすびのかみ」から名前がつけられたといいます。
他人丼と開化丼

| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 呼び名 | 開化丼 | 他人丼 |
| 材料 | 牛肉や豚肉と卵 | 牛肉や豚肉と卵 |
| 由来 | 文明開化の時代に牛肉が食べられるようになったことから | 親子ではないので「他人」丼 |
鶏肉と卵を入れて作った丼ものと言えば親子丼ですよね。
卵とにわとりが親子なことから親子丼という言葉は生まれましたが、鶏肉の代わりに牛肉や豚肉と卵で作った丼ものは、親子ではないので関西では他人丼と呼んでいます。
しかし関東では他人丼のことを開化丼と呼んでいます。開化丼の開化とは文明開化のことを指します。
文明開化の時代に牛肉が食べられるようになってきたことから、文明開化の丼ということで、豚肉や牛肉に卵を使って作った丼は、開化丼です。
コーヒーに入れるのは?:関西ではフレッシュ、関東はミルク
| 関東 | 関西 | |
|---|---|---|
| 呼び名 | ミルク | フレッシュ |
| 由来 | 一般的な呼び方 | メロディアン社が「コーヒーフレッシュ」として広めた |
コーヒーを飲むときに入れるものと言えば生クリームですが、関東ではその生クリームのことをミルクと呼んでいます。関西ではミルクとは呼ばずにフレッシュと呼んでいます。
どうしてミルクがフレッシュなのか?疑問がわきますが、フレッシュという名前は商品から来ています。
コーヒーミルクのメーカーである「メロディアン」ではミルクのことをコーヒーフレッシュと呼んで、関西に広めました。
しかし関東にはフレッシュという言葉がそれほど広まらず、今に至ったようです。
味だけでなく名前も違うから面白い
濃い味の関東に薄い味の関西、古くから味にかなりの違いがあり、それぞれ作り方にはこだわりがある関東と関西。味はもちろん、呼び方にも違いがあることがわかります。
同じもののはずなのに名前が違うなんて・・・と戸惑う方もいらっしゃるでしょう。
でもだからこそ面白いと思いませんか?同じ名前なのに違うものだという例はいくつもあります。
どうしてその名前が付けられたのか、由来を見てその食べ物の歴史を知るのも面白いですよ。