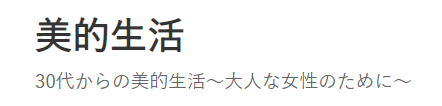穴子はどうやって食べる?と聞かれれば、お寿司や天ぷらが浮かぶという方が多いでしょう。でも、同じお寿司でも関東と関西では穴子の食べ方が違うことは知っていますか?
穴子の関東風の食べ方は煮穴子、そして関西風の食べ方は焼き穴子です。煮たものと焼いたものでは食感も変わってきますよね。関東と関西それぞれの穴子の食べ方と好みが違う理由についてまとめました。
煮穴子、天ぷらが主流の関東

| 食べ方 | 特徴 |
|---|---|
| 煮穴子 | 甘めの味付けが好まれる |
| 天ぷら | 特大の穴子を使用することがある |
| 沢煮の穴子 | 短時間で煮る、仕上がりが白い |
| 長時間煮穴子 | 長時間煮る、色が濃い茶色、トロトロで溶けてしまいそうなほど柔らかい |
| 穴子寿司 | 江戸前寿司のネタとして人気 |
関東の穴子の主な食べ方は煮穴子と天ぷらです。関東の料亭やお寿司屋さんに行くと、特大の穴子の天ぷらを売りにしているところもありますし、煮穴子は少し甘めなものが好まれます。
穴子のお寿司は江戸前寿司のネタの中でも人気があるもののひとつです。
少し小さめの穴子は天ぷらに向いていると言われています。煮穴子は煮方にいくつかの方法があります。短時間で一気に煮る沢煮の穴子は醤油の色が染み込まないため仕上げが白く上がります。
その反対に長時間かけてしっかり煮て作った穴子は、色も濃い茶色になっていますし、トロトロになって溶けてしまいそうなぐらい柔らかく仕上がります。
関西では焼き穴子が好まれる

| 食べ方 | 特徴 |
|---|---|
| 焼き穴子 | 香ばしい香りとパリッとした食感が特徴 |
| 干物 | 大きい穴子を干物にすることもある |
| 刺し身 | たまに穴子を刺し身にして食べる |
| 季節的特徴 | 初夏から10月の穴子は脂が控えめでファンが多い |
| 蒲焼・白焼き | 穴子は蒲焼や白焼きにして食べることが多い |
| うなぎとの違い | 穴子は海水魚である点がうなぎの淡水魚との大きな違いです |
関西で好まれている穴子の食べ方はなんといっても焼き穴子ですが、大きい穴子は干物にすることもありますし、たまに刺し身にして食べることもあります。初夏から10月までの焼き穴子は脂も控えめでファンが多いです。
関東では柔らかい食感の穴子ですが、関西では焼きますから香ばしい香りとパリッとした食感が特徴です。穴子は蒲焼や白焼きにして食べることが、関西では多いです。
ちなみに穴子と形が似ているうなぎも蒲焼にしたり白焼きにして食べますよね?焼いたものを見ると、穴子なのかうなぎなのか、ぱっと見ただけでは区別がつきません。
でも穴子とうなぎは種類が違いますよ。うなぎは淡水魚ですが穴子は海で育つ海水魚ですからお間違いなく。
広島名物「穴子飯」とは

| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 名称 | 広島名物「穴子飯」 |
| 主要な食材 | 蒲焼にした穴子、穴子のあらでとっただし汁 |
| ご飯の特徴 | 醤油味ベースで炊かれる |
| 誕生背景 | 明治時代に駅弁として生まれた |
| 提供地域 | 広島、特に宮島周辺に多い |
| 店による違い | タレと焼き方が店によって異なる |
| 楽しみ方 | 広島や宮島を訪れた際に、穴子飯を食べ歩きするのも一つの楽しみ方 |
| テイクアウト | 可能な店が多いため、食べ歩きしやすい |
関西では「丼」も人気が高く、穴子がのった「丼」でもっとも有名なのが広島名物の「穴子飯」です。
「穴子飯」の中には蒲焼にした穴子、そして穴子のあらでとっただし汁で炊いた醤油味ベースのご飯が特徴です。穴子飯は明治時代に駅弁として生まれました。
今は広島の中でも宮島周辺に「穴子飯」を出している店が多くあります。基本の作り方は同じでも店によってタレも焼き方も違いますから、宮島に行ったら穴子飯を食べ歩きして楽しむのも良いかも。
穴子飯はテイクアウトすることができる店も多いですから、食べ歩きしやすいですよ。
スポンサーリンク
関東と関西で食べ方が違う理由

| 地域 | 穴子の特徴 | 食べ方の選択理由 | 一般的な食べ方 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 脂がのっていて大ぶり | 煮ることで適度に脂が落ちてふっくらと美味しくなる | 煮穴子 |
| 関西 | 小ぶりで脂が少なめ、皮が多い | 煮ると硬くなるため焼く方が美味しい。皮を焼くことでパリッとした食感を楽しめる | 焼き穴子 |
関東と関西で穴子の食べ方に違いがあるのは、関東と関西の穴子の特徴が違うことが理由です。関東の穴子は脂がのっていて大ぶりのものが多いです。
ですから、煮て食べることによっていい感じに脂が落ちて、ふっくらと美味しくなるのです。
一方、関西の穴子は関東に比べると大きさが小ぶりで脂も少なめです。脂が少ない穴子は煮ると硬くなってしまうため、煮るより焼くほうが美味しくいただけます。
また、関西の穴子は皮が多いですから、こんがり焼き上げたほうが、パリッとした食感を楽しめます。
押し寿司は関西だけ!お寿司の違い

| 特徴 | 関東 | 関西 |
|---|---|---|
| 握り寿司のスタイル | 寿司職人が一手間かけて味付けする。江戸前寿司が代表例。 | 素材の味を生かしたシンプルな味付けが特徴 |
| 寿司に対するアプローチ | 職人の技を見せるため、醤油無しでそのまま食べることが多い。 | 素材の味を活かすため、さっと塩をふるなどシンプルな味付け |
| 穴子の扱い | しっかり醤油で煮た穴子を使用する。 | 焼き穴子を使用し、素材の味を楽しむ。 |
お寿司は握りだけでなく、ちらし寿司や押し寿司、巻き寿司などいろいろな形がありますよね。関東でも関西でもお寿司はいろいろな食べ方をします。
けれど関西地方には当たり前のようにある穴子の押し寿司ですが、関東の人は知りません。関東では穴子と言えば煮穴子をのせたにぎりだけで、押し寿司があるのは関西だけのようです。

関東と関西では握り寿司のスタイルも違います。関東では職人が一手間かけてひとつひとつ味付けを変えて出します。江戸前寿司は寿司職人の力量の見せ所なのです。
ですから、ただ具をのせると言うだけでなく、ヅケにするものもあればタレをぬったものもあり、酢でしめるものもあり、と特に醤油をつけなくても味がついているので醤油をつけずにそのまま食べる人も多いです。
関東の穴子寿司はしっかり醤油で煮てありますから、たしかに醤油無しで食べますよね。
でも関西では職人の技を売りにすると言うよりも素材で勝負です。旬の素材の味を楽しんでもらおうと、特に味をつけずにさっとお塩をふるだけなど、味付けもシンプルです。
関西の穴子寿司もしっかり醤油の味をついた煮穴子でなく、焼き穴子ですから素材の味を楽しめそうですね。
煮穴子も焼き穴子もどちらも美味しい!
関東と関西、同じ穴子なのに味が違いますから、はじめて食べた人はびっくりするかも。でも新たな味も美味しいですし、穴子をさらに好きになりますよ。
関東の煮穴子と関西の焼き穴子、駅弁ではその両方の味を楽しむことができる「あなごあいのせ重」も売られています。両方の味を一度に楽しみたい、という方はぜひお楽しみください。
「あなごあいのせ重」は三原駅と福山駅で売られていますよ。