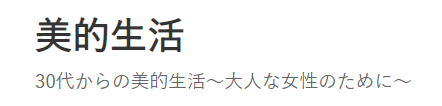飲食店のメニューを見ると、単品のメニューのほかに「とんかつ定食」や「唐揚げ定食」「焼き魚定食」など、いろいろな定食のメニューが並んでいますよね。
おかずだけでなくご飯もついていてしっかり満足できる定食メニューは、単品よりも好きと言う人は多いのではないでしょうか。でも、あらためて「定食とは?」と聞かれると、答えられますか?
定食のほかに「セット」がある場合には、違いも気になるところです。定食とは、セットとの違いやどのようにして生まれたのかなど、定食についてまとめました。
定食とは

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本構成 | ごはん、汁物(例:みそ汁)、おつけもの、おかず |
| おかず | 肉、魚、野菜などが一般的。メインのおかずが定食の名前になることも多い |
| 中心の食材 | ご飯(ご飯を中心におかずが組み合わされる) |
| サービング方法 | コース料理とは違い、すべてのお皿が同時に並べられる |
| 目的 | どのおかずもご飯と合うように、一緒においしく食べられるように考慮されている |
| ご飯の役割 | どんなおかずにも合う特別な食べ物とされ、定食の中心となる |
定食は日本で普段食べている定番の食事のスタイルとなっています。まずはお米を炊いた「ごはん」があって、みそ汁などの「汁物」があり、香の物としておつけものが添えられます。
そこまではどの定食も同じで、違うところがおかずです。おかずとして、定食には肉や魚、野菜などのメインのおかずがあります。
定食はそのおかずの名前の後に「定食」という言葉がついてメニューに出ていますよね。なので定食の中心はおかずであるようなイメージがありますが、定食の中心は実はおかずではなくご飯です。
日本人が主食として日常食べているご飯、このご飯を取り囲むような形で定食は並べられています。
コース料理のように一品ずつ運ばれるのではなく、すべてのお皿が同時に並んでいる形が定食です。
どのおかずもご飯と合うように、一緒においしく食べることが出来るように考えて作られている「定食」。
おかずどうしで合うもの、合わないものはあっても、ご飯はどんなおかずにも合う特別な食べ物ですよね。定食はそんなご飯を中心に、いろいろなおかずを組み合わせて作られています。
定食の起源

| 時代 | 定食の起源と影響 |
|---|---|
| 弥生時代 | 米が主食となり、食文化が発展する始まり |
| 平安時代 | 貴族の大饗料理、神饌料理などが登場 |
| 禅宗 | 動物性食品を避けた精進料理が僧侶たちによって食べられる |
| 武士の時代 | 本膳料理が武士の間で広まる |
| 江戸時代 | 参勤交代の武士や独身男性のための定食屋が登場。現在の定食スタイルが確立 |
| 近現代 | 食生活や産業の発展によって、定食がさらに庶民に広がり現在の形に |
定食の中心である米を日本人が食べるようになったのは弥生時代です。これまで狩猟や採集生活をしていた人々は農耕するようになり、自分で作った米を中心として食文化が発達していきます。
その後、豊作や大漁を祈ったり収穫の感謝、神様への供物として神饌料理、平安時代には上流階級の貴族の食事としてご飯のほかにお皿に入ったいろいろな料理が盛り付けられた大饗料理、
禅宗の僧侶たちの動物性食品を食べない精進料理、武士が食べるお膳にご飯とおかずが並べられた本膳料理が生まれます。
スポンサーリンク
現在の日本の食事スタイルが確立されたのは江戸時代だと言われています。
参勤交代をしている武士たち、独身や単身の男性のために定食屋が生まれ、現在のようにご飯、汁物、主菜、漬物が並ぶ定食が出回るようになります。
食文化が発展し、定食は武士だけ得なく庶民にも広がるようになりました。その後、食生活の変化や産業の発展によって影響を受けながら、現在のような定食のスタイルが生まれて今に至ります。
定食とセットの違い

| 項目 | 定食 | セット |
|---|---|---|
| 主菜 | あり(例:肉、魚) | あり(例:肉、魚) |
| 付属の食品 | ご飯、汁物(例:みそ汁)、香の物(例:おつけもの) | 主菜に加えて何か一つ以上 |
| 和食の場合 | ご飯、汁物が一般的 | ご飯または他の何かがつく場合もある |
| 洋食の場合 | 不一般 | パンとスープが一般的 |
| メニューにのっている名前 | 定食と明記 | セットと明記 |
| 注意点 | 汁物がない場合、厳密には定食ではない | 主菜に何か一つでもついていればセットとされる |
単品の料理と定食の違いははっきりわかりますが、よくわからないのが定食とセットの違いですよね。
定食もセットも、飲食店のメニューを見るとどちらもありますから良くわからなくなってしまいますよね。
ファミレスでは和食のメニューと洋食のメニューがあります。和食のメニューの場合はご飯とお味噌汁などの汁物がつき、洋食のメニューではパンとスープがついています。
それならば和食は定食、洋食はセット?と思ってしまいますが、どうやら内容をよく比べてみると定食とセットには違いがあります
定食の場合についてくるのは主菜のほかにご飯、汁物、香の物ですが、セットの場合は主菜のほかに何か一つでもついていればいいようです。
定食とセットの違いについてはあいまいに考えている飲食店もあり、主菜のほかにご飯がついていて汁物はついていなくても定食としてメニューに載せているところもあるようですが、正確に言えばそれは定食ではなくセットです。
ご飯を中心においしく食べよう
ご飯を食べておかずを食べる、今度は汁物を飲んでまたご飯に戻る、ご飯を中心に食べることが出来る定食スタイルは、ご飯を間に入れることによってよりおかずの味をおいしく感じさせてくれます。
海外ではコース料理のように一品ずつ料理が出てきますが、一度に全部出てくることによってどの料理もちょっとずつ楽しみながら食べることが出来る日本ならではの定食。
バランスも良いですから定食はおすすめですよ。定食料理を食べて健康的な食生活を送ってくださいね。