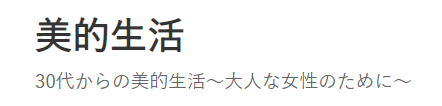煩悩を捨てる、煩悩に惑わされるなど、煩悩という言葉はよく耳にしますよね。
でも、「煩悩ってどういう意味?」と聞かれると答えにつまってしまう方も多いのではないでしょうか。
普段よく使う言葉でも、改めてその意味は何かと考えてみるとわからない、ということはよくあります。
煩悩もそんな言葉のひとつ。間違った使い方をしないためにも、ここで改めて煩悩とは何かについて理解しておきましょう。
煩悩とは?

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 煩悩の意味 | 仏教用語で心や身体を乱す欲望や妄念 |
| 欲と煩悩 | 欲は悪くないが、目標達成の妨げになる場合がある |
| 煩悩の語源 | 「わずらわしい」と「悩み」 |
| 挑戦と煩悩 | 挑戦する際に躊躇や迷いを引き起こす |
煩悩は仏教用語のひとつで「心身にまとわりついて心を乱す妄念や欲望」と言う意味です。
人は誰しも欲を持っています。欲は悪いものではないのですが、何かを成し遂げようというときに邪魔になることがあります。それが煩悩です。
言葉を詳しく見ていくと、煩悩の煩には「わずらわしい」、脳には「悩み」という意味があります。
何かに挑戦しようと思ったとき、人は躊躇することがあります。人が躊躇して挑戦するかどうか迷ったときにその人の頭の中をしめているのが煩悩です。
煩悩の数・種類

煩悩の数
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 煩悩の数 | 108個とされる |
| 108の理由 | 理由は諸説あり、明確な答えはない |
人の煩悩は108個あると言われています。どうして108と決められたのでしょうか。煩悩の数が108と決まった理由は諸説あります。代表的なものをご紹介しましょう。
六根説(ろっこんせつ)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 六根(ろっこん) | 目、耳、鼻、舌、身、意(心) |
| 六塵(ろくじん) | 色、声、香、味、触、法 |
| 六塵の具体的内容 | 映像、音声、におい、味、触感、心の動き |
| 感情の分類 | 好、悪、平(良い、悪い、どちらでもない) |
| 感情の性質 | 染(汚い感情)、浄(清らかな感情) |
| 時間軸 | 過去、現在、未来 |
| 108の計算式 | 6(六塵)× 3(好、悪、平)× 2(染、浄)× 3(過去、現在、未来) |
| 108の意義 | 六根説に基づき、感情は108に分かれるとされる |
人間の五感である目、耳、鼻、舌、身に心である意を加えたものが六根です。六根は六塵(ろくじん)を生むという考え方があります。
六塵とは、色、声、香、味、触、法のことです。
文字だけ見てもわかりにくいですが、それぞれ映像、音声、におい、味、触感、そして心の動きを指します。
六塵はさらに好、悪、平つまり、良い、悪い、どちらでもないの3種類に分かれ、さらにそれぞれが汚い感情を示す染と清らかな感情を示す浄に分かれます。
そしてさらにそれはそれぞれ過去、現在、未来に分かれます。
六塵(6種類)x好、悪、平(3種類)x染、浄(2種類)x過去、現在、未来(3種類)=108
この計算式が成り立つことから、六根説では感情は108に分かれるとしています。
十纏(じってん)・九十八結(くじゅうはっけつ)説
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 十纏(じってん) | 無慚、無愧、嫉、慳、悔、眠、掉挙、こん沈、忿、覆 |
| 結(けつ) | 煩悩の別の呼び方であり、98種類がある |
| 十纏と九十八結の合計 | 10(十纏) + 98(九十八結) = 108 |
| 108の意義 | 十纏と九十八結を合わせて、煩悩は108に分かれるとされる |
無慚(むざん)、無愧(むき)、嫉(しつ)、慳(けん)、悔(け)、眠(みん)、掉挙(じょうこ)こん沈(こんじん)、忿(ふん)、覆(ふく)という人間を苦しませる煩悩を十纏といいます。
煩悩の別の呼び方には「結」があり、この結は合わせて98あると言われています。そのため、十纏(10種類)と九十八結を合わせて108となります。
四苦八苦説
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 四苦 | 生、老、病、死 |
| 八苦 | 愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五蘊盛苦 |
| 四苦八苦の起源 | 四苦と八苦から作られた仏教用語 |
| 108の計算式 | 4(四苦)x 9 + 8(八苦)x 9 = 108 |
| 108の意義 | 四苦と八苦を元に、煩悩・苦しみは108に分かれるとする説 |
四苦八苦とはよく使いますよね。この言葉も仏教から来たものです。人間につきものである8種類の苦しみ
スポンサーリンク
- 四苦:根本的な苦しみである生(しょう)・老・病・死
- 愛別離苦(あいべつりく) 愛する者と別離すること
- 怨憎会苦(おんぞうえく) 嫌いなものと出会う苦しみ
- 求不得苦(ぐふとくく) 求めるものが得られない苦しみ
- 五蘊盛苦(ごうんじょうく) 五蘊(心身の苦痛)が盛んに起こる苦しみ)
から四苦八苦という言葉が作られました。四苦八苦、つまり4×9+8×9で108とする説です。
除夜の鐘とは
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 除夜の鐘 | 大晦日にお寺で鳴らされる鐘 |
| 鳴らす回数 | 108回 |
| 108の意味 | 煩悩の数が108あるから |
| 鳴らすタイミング | 107回は大晦日、最後の1回は新年が明けたとき |
| 願い | 新年が煩悩に惑わされないようにという願いが込められている |
毎年大晦日になるとお寺でつく除夜の鐘は、鳴らす数が108と決まっていますよね。それは煩悩の数が108あるからです。
除夜の鐘は107回まで大晦日のうちについて、年が明けたときに最後の1回をつきます。除夜の鐘には新年が煩悩に惑わされませんようにという願いが込められています。
「三毒」とは?
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 三毒 | 貪(とん)、瞋(しん)、癡(ち) |
| 貪(とん) | 欲、お金が欲しい、褒められたいなど |
| 瞋(しん) | 怒り、衝動的な行動が引き起こす苦しみ |
| 癡(ち) | 愚痴、他人の幸福をねたむ、不幸を面白がるなど |
| 目的 | これらの三毒をなくすことで、人はゆったりと生きられる |
煩悩の中でも人間を最も苦しめるものは「三毒」と呼ばれています。それが貪(とん)、瞋(しん)、癡(ち)です。少々難しい言葉ですが、この貪、瞋、癡は「欲」「怒り」「愚痴」を表します。
お金がほしい、褒められたい、そのためには人がどうなってもいいと人を騙したり押しのけたりする「欲」、腹が立って言ってはいけないことを言ったりやってはいけないことをして人生をダメにしてしまう「怒り」、
幸せそうな人を見るとねたましく不幸を面白がる「愚痴」ーこの3つの煩悩をなくすと、人はゆったりと生きていくことができるでしょう。
煩悩の使い方

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 煩悩の一般的な使い方 | 欲や怒りなどの負の感情に取りつかれている状態 |
| 使われる文脈1 | 「煩悩にまみれる」、「煩悩のかたまりみたいな人」 |
| 使われる文脈2 | 「煩悩にさいなまれる」、怒りや欲、ねたみに苦しむ時 |
| 子煩悩 | 子供を非常にかわいがる親を指す、良い意味で使われる |
煩悩という言葉は、「煩悩にまみれる」「煩悩のかたまりみたいな人」というように、欲などにとりつかれた悪い人を表すときによく使われます。
また、「煩悩にさいなまれる」など、怒りや欲、ねたみなどの悪感情に苦しめられているときにも使われます。いずれも煩悩はあまりいい意味では使われていません。
けれど煩悩は悪い意味にしか使われないわけではありません。子煩悩という言葉がありますよね。
子煩悩とは親ばかと言われるぐらい、子供を非常にかわいがっている親を表す比喩表現ですが、こちらは決して悪い意味では使われていません。
子供が大好きで、子供を大事に思っている良き親の意味で使われています。
「煩悩を捨てる」とは?

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 煩悩を捨てるとは | 欲や怒り、執着などの負の感情を手放すこと |
| 捨てる結果 | 欲を持たなくなり、怒りや執着がなくなる |
| 難易度 | 普通の人がすべての煩悩を捨てることは難しい |
| 生活への影響 | ストレスが減り、気持ちが穏やかになる |
| 経済的な影響 | お金が無駄に減ることがなくなる |
| 総合的な影響 | 良い流れが生まれ、自分自身だけでなく他人にも良い影響を与える |
人の心を惑わせる煩悩、そんな煩悩を「捨てる」とはいったいどういうことなのでしょうか。
人は欲が強すぎると自分のコントロールができなくなる結果、人を傷つけます。
自分の欲や愚痴、怒りばかりで人のことを考えずに自己中心的でいれば最終的には自分の身を滅ぼすこともあるでしょう。
煩悩を捨てると人は欲を持たなくなり、怒りや執着がなくなります。普通の人がすべての煩悩を捨てることは難しいです。
けれど、煩悩を捨てて執着や欲がなくなれば、人はストレスがなく気持ちも穏やかになり、お金が無駄に減ることもなくなり、良い流れが生まれます。
捨てられなくてもコントロールを

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 煩悩のコントロール | 煩悩をすべて捨てるのは難しいが、コントロールは可能 |
| コントロールの重要性 | 煩悩にまみれると自己破壊の可能性がある |
| 除夜の鐘の効果 | 108回の除夜の鐘を聞くことで心が落ち着き、煩悩を払う機会ができる |
| 年末の願い | 除夜の鐘を聞きながら新年に向けての願いを持つ |
悟りの境地に達している人であれば煩悩をすべて捨てているかもしれませんが、なかなか煩悩をすべて捨てることはできません。
ある程度であれば煩悩をコントロールすることもできます。煩悩にまみれているといつかは自分を苦しめることになりますから、上手にコントロールするよう心掛けたいですね。
108つの除夜の鐘を聞くと、なんとなく落ち着いた気持ちになるものです。年末は除夜の鐘を聞きながら、煩悩を少しずつ払い、新たな年が良い年になることを願いましょう。