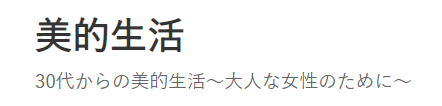丼物は具がどっさりのっていてボリュームたっぷりで本当においしいですよね。定食もいいけれど、お店で食べるなら丼物をいつも注文しちゃうという方も多いのではないでしょうか?
丼物の中でも何が好き?と言われたら親子丼や牛丼などがすぐ頭に浮かびます。親子丼や牛丼など、どこの地域でも食べられている全国区の丼もいいですが、地域に特有の丼も旅の楽しみですよね。
旅行でお昼ご飯を食べようと食堂に入ってメニューを見てみると、見たことがない名前の丼があったりします。
写真を見てみるとお魚や肉がどっさりのっていて、見ただけで食べたくなります。そんな地域特有の丼の中でも、人気がある丼に木の葉丼やしのだ丼などがあります。
木の葉丼やしのだ丼と聞いて、ああ、あれはおいしいよねと答える人もいれば、え?それ何の丼?と答える人もいるでしょう。
どんな丼なのか、どこで食べられるのか知りたい!人気の木の葉丼やしのだ丼、そして衣笠丼など地方特有の丼について調べました。
木の葉丼とは
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 地域 | 関西 |
| 主な食材 | 薄く切ったかまぼこ、青ネギ |
| 追加の具材 | シイタケ、三つ葉、たけのこ |
| 味付け | だしにしょうゆ、みりん |
| 代替食材 | さつま揚げ(なか卯の場合) |
| 名前の由来 | 不明(かまぼこを木の葉に見立てた説など) |
| 作り方の要点 | 1. かまぼこと玉ねぎをめんつゆで煮込む |
| 2. 溶き卵を入れる | |
| 3. かいわれ大根を散らす | |
| 用途・出現場所 | 家庭料理、うどん屋、定食屋の定番メニュー |
関西地方でよく食べられている丼に木の葉丼があります。木の葉丼とは卵丼の中にかまぼこやさつま揚げなどが入っている丼です。
シンプルで入っている食材は安価なものばかり。庶民的な木の葉丼は関西地方では家庭でよく作られている料理の一つですし、うどん屋さんや定食屋さんの定番メニューとなっています。
木の葉丼という名前はどうしてついたのか、名前の由来ははっきりこれというものはありません。けれど木の葉丼の中には本物の木の葉は入っていません。
木の葉という名前は、かまぼこを木の葉に見立てたんじゃないか、という説と中に入っている三つ葉などの具が木の葉と考えられたのではないか、と言う説があります。
木の葉丼の中に入っている食材は、薄く切ったかまぼこ、青ネギ、が基本です。それ以外の具材としてはシイタケ、三つ葉、たけのこなどがあります。
外食チェーンストアのなか卯で出している木の葉丼の中には、かまぼこではなく薄切りしたさつま揚げが入っています。木の葉丼の味付けにはだしにしょうゆ、みりんが使われます。
木の葉丼は簡単に作ることが出来ます。まずはかまぼこと玉ねぎをめんつゆの中に入れて煮込みます。その中に溶き卵を入れ、最後にかいわれ大根を散らせばできあがりです。
しのだ丼とは
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 地域 | 関西 |
| 主な食材 | 油揚げ、かまぼこ、青ネギ |
| 代替食材 | さつま揚げ、なると、ちくわ |
| 味付け | だしとしょうゆ |
| 名前の由来 | 信太の森ときつねの伝説(油揚げがきつねの好物) |
| 作り方の要点 | 1. 油揚げとかまぼこ、青ネギをだしとしょうゆで煮る |
| 2. 3分ほど煮たら完成 | |
| 3. 残りの汁をかけて食べる | |
| 用途・出現場所 | 家庭料理、地域の食堂など |
油揚げを使った丼をしのだ丼といいます。しのだ丼は漢字で信太丼または信田丼と書きます。しのだ丼は関西地方でよく食べられている丼です。
どうしてしのだ丼という名前が付いたのか、しのだ丼の「しのだ」は現在の大阪府にある「信太の森」から来ています。
信太の森は葛の葉ぎつねの伝説で有名です。きつねといえば油揚げが好物だと言われていますよね。ということから、油揚げが入っている丼は「しのだ丼」と呼ばれるようになったようです。
しのだ丼の中に入っている具材は、油揚げにかまぼこ、青ネギです。かまぼこの代わりにさつま揚げやなると、ちくわを使ってもおいしく作ることが出来ます。味付けはだしとしょうゆを使います。
作り方はこれも簡単で、一口大に切った油揚げと薄切りにしたかまぼこに青ネギをだし汁と醤油を混ぜて作ったつゆの中に入れて3分ほど煮たらできあがり。具をのせたら最後に残りの汁をかけて食べます。
衣笠丼
スポンサーリンク
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 地域 | 京都 |
| 主な食材 | 油揚げ、九条ネギ、卵 |
| 味付け | だし汁、酒、みりん、しょうゆ |
| 名前の由来 | 京都の「衣笠山」から、きぬをかけた伝説に基づく |
| 作り方の要点 | 1. 細く切った油揚げをだし汁で煮込む |
| 2. 醤油、酒、ねぎを追加して煮込む | |
| 3. 卵を流し込んでとじる | |
| 用途・出現場所 | 家庭料理、京都の食堂やレストラン |
油揚げとねぎを卵とじにしてご飯の上にかけた丼が衣笠丼です。衣笠丼は京都生まれのご当地丼で、大阪で食べられているきつね丼と中身は同じです。
衣笠丼という名前は京都の「衣笠山」から来ています。真夏に雪景色にしようと宇多天皇が衣笠山に白い絹をかけたという話が残っています。
その話から「衣笠山」は「きぬかけ山」とも呼ばれているのですが、油揚げの上に卵をふんわりとかけて作った丼は、きぬをかけた衣笠山と似ているということから、この衣笠丼という名前がつけられました。
衣笠丼の食材は油揚げに九条ネギ、卵、味付けにはだし汁、酒、みりんやしょうゆが使われます。衣笠丼の作り方は細く切った油揚げをだし汁の中で煮込んでから醤油や酒、ねぎを入れてさらに煮込み、卵を流し込んでとじたら完成です。
ハイカラ丼
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 地域 | 主に大阪 |
| 別名 | たぬき丼(他の地域での名称) |
| 主な食材 | 天かす、長ネギ、卵 |
| 味付け | だし汁、しょうゆ、みりん |
| 名前の由来 | 大阪で天かすを「ハイカラ」と呼ぶため |
| 作り方の要点 | 1. 斜め切りした長ネギをだし汁で煮る |
| 2. 天かすを加える | |
| 3. 卵を全体に回し入れる | |
| 出現場所・用途 | 大阪の食堂、家庭料理 |
天かすをたまごでとじて作った丼がハイカラ丼です。ハイカラ丼は主に大阪で食べられています。天かすがのったそばのことをたぬきそばといいますよね。ということから、ハイカラ丼はほかの地域ではたぬき丼と呼ばれています。
どうしてハイカラ丼という名前が付いたのか、それは天かすのことを大阪ではハイカラと呼んでいるからではないか、と言われています。
東京ではたぬきそばといえば天かすが入ったそばのことですが、大阪では油揚げをのせたそばのことをたぬきと呼びます。
ということから、たぬきと言われて油揚げが入った丼だと間違われることがないように、大阪では天かすが入ったものをハイカラと呼ぶようになったようです。
ハイカラ丼の具材は天かすに長ネギ、そして卵です。味付けはだし汁にしょうゆ、みりんなどを使います。
作り方はだし汁にしょうゆ、みりんなどを混ぜて作った汁の中に斜め切りした長ネギを入れ、長ネギがくたっとなったところに天かすを加え、卵を全体に回し入れます。
若竹丼
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 地域 | 関西地方 |
| 名前の由来 | 若竹煮(新たけのこと新わかめ)から |
| 主な食材 | たけのこ、ワカメ、卵、ちくわ、ネギ |
| 味付け | だし汁、しょうゆ、みりん |
| 作り方の要点 | 1. たけのこ、ちくわ、ネギをだし汁で煮る |
| 2. ワカメを加えてさっと火を通す | |
| 3. 卵でとじる | |
| 出現場所・用途 | 関西地方の食堂、家庭料理 |
筍とワカメを卵でとじて作った丼を若竹丼と言います。これも関西地方でよく食べられるどんぶりになります。
名前の由来は、木の芽を連想させる新たけのこと新わかめで作る若竹煮から来ています。
若竹丼の食材はたけのことワカメ、卵にちくわやネギ、味付けはだし汁にしょうゆ、みりんなどです。
作り方は、だし汁の中に水煮のたけのこ、ちくわにネギを入れて煮たら、ワカメを入れてさっと火を通して卵にとじます。
シンプルでおいしい関西の味、外でも家でも楽しもう
お肉やお刺身などが豪華にのった丼もいいですが、野菜たっぷりでヘルシー、シンプルな丼もよいものです。
関東の人にはなじみがあまりないかもしれませんが、木の葉丼にしのだ丼、ハイカラ丼に若竹丼はどれもおいしくておすすめですよ。
定食屋さんやうどん屋さんで食べるのもいいですし、家庭で作ってみるのもいいでしょう。
具材もどれも簡単に手に入るものばかりですから、思い立ったらすぐに作ることが出来ます。
木の葉丼やしのだ丼、ハイカラ丼、若竹丼を普段食べる定番メニューに取り入れましょう。